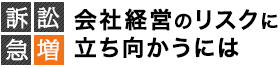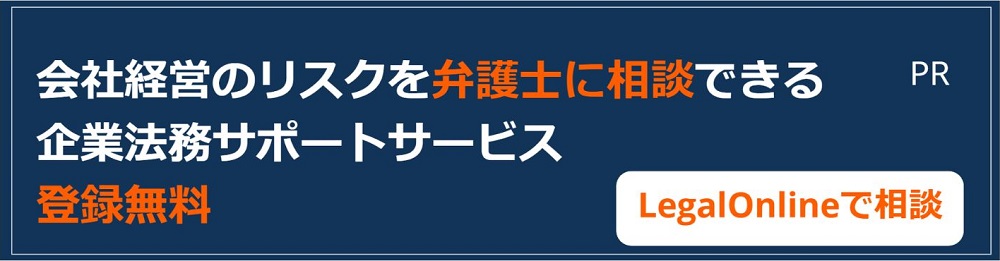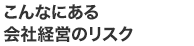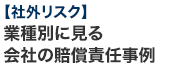先に紹介したA社の大火災では、被害総額が200億円であったことに対して、火災保険から支払われた保険金は45億円でした。45億円という金額だけを見れば高額ですが、倉庫の存続を考えた場合、保険プランとしては失敗だったと言わざるを得ません。
なぜ、この例において適切な保険プランの設定がなされていなかったのでしょうか? その理由こそ、法人向けの火災保険に加入する際のポイントにもなります。
■物件の状況をしっかりと確認する
A社の火災被害が拡大した大きな理由は、次の通りです。
- 窓が少なく消防隊の侵入口が限られた
- 保管物に燃えやすい紙素材のものが多くあった
- 火元の近くにスプリンクラーがなかった
- 太陽光パネルを増設するなどしたため、消防活動の妨げとなった
A社は、これら倉庫の現状をしっかりと把握した補償内容にすべきでした。あるいは、これら倉庫の現状を改善すべきでした。補償を手厚くするか、もしくは消防対策をしっかりと行なうか、どちらかの対策を打っていれば、A社における被害総額は大幅に抑えられたことでしょう。
法人向け火災保険を検討する場合、または更新する場合には、その時々の物件の現状を正確に把握することが大前提です。
■何を重点的に補償して欲しいのかを決める
複数の物件を保有している場合には、何を重点的に補償して欲しいのかを決めるようにしましょう。
「設備の一部を失ったとしても、建物だけは絶対に守りたい」「建物はプレハブなので、設備や什器を主に守りたい」「完成品を多く保管しているため、とにかく商品だけは守りたい」などです。
重点を置く項目に応じて、物件ごとの補償内容に強弱をつけることができるでしょう。
これによって、すべての物件に一律で保険をかけるよりも、保険料を大幅に節約することができるはずです。
■適切な免責額にする
免責額とは、万が一火災等によって被害が生じた際の、法人による自己負担金のこと。保険金は、免責額を超過した部分のみ支払われる仕組みになります。
たとえば、免責額が1000万円で1500万円の被害が生じた場合、支払われる保険金は差額の500万円になります。
もちろん、免責額が大きければ大きいほど、万が一の補償額は小さくなります。一方で、免責額が大きいほどに保険料は安くなるというメリットもあります。
保険料を節約する目的で、免責額を高く設定する経営者もいるようです。しかしながら、万が一の時に備え、保険料が多少高くなったとしても免責額はほどほどにしておくことをお勧めします。