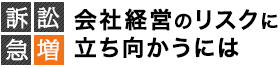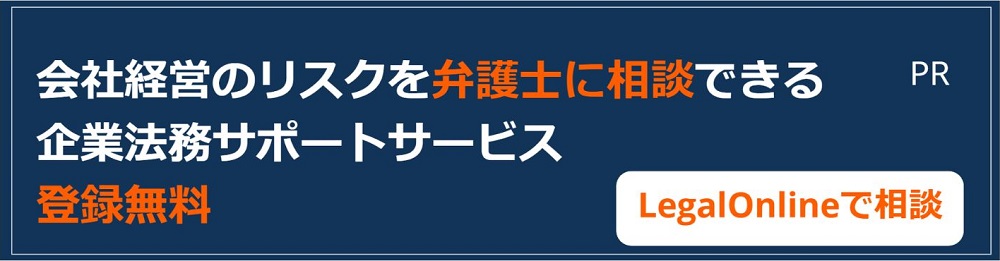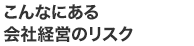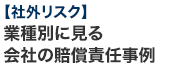中退共とは「中小企業退職金共済」の略で、国が昭和34年に中小企業対策の一環として制定した「中小企業退職金共済制度」に基づいて設けられた退職金制度です。単独で退職金制度を設けることが難しい中小企業の実情を考慮し、事業主との相互共済のしくみと国の援助によって退職金制度を設けることで中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、中小企業を振興することを目的としています。2018年1月末現在では、36.7万所以上の企業が加入し、運用資産額はおよそ4.9兆円となっています。
中小企業退職金共済の制度や掛金とは

中小企業退職金共済
中小企業退職金共済制度に基づいて設けられた退職金制度
中退共とは、主に中小企業を対象に国が運営する退職金制度です。ここでは中退共の制度や掛金について解説します。
中退共とは
中退共のしくみ
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月掛金を納付します。従業員が会社を辞めることになり退職金の支払いが必要となる場合は、中退共から従業員に直接退職金が支払われます。
加入条件とは
中退共はメリットが大きい制度ですが、誰でも加入できるわけではありません。中小企業の振興を目的とする制度であるため、加入できるのは中小企業に限られています。主な対象は次の通りです。
| 業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 |
|---|---|---|
| 一般業種(製造業、建築業等) | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
ここでいう常用従業員数とは、1週間の所定労働時間が同じ企業で雇用されている通常の従業員とおおむね同じであり、雇用期間の定めがない者や雇用期間が2ヶ月を超えて雇用されている者を含みます。従業員の全員加入が原則となっていますが、次の条件に当てはまる場合は加入させなくてもよいことになっています。
- ・期間限定の従業員
- ・試用期間中の従業員
- ・短時間勤務の従業員
- ・休職期間中の従業員
- ・定年が近い従業員
掛金
掛金は全額事業主が負担することになっています。どのような理由があっても、従業員に負担させることはできません。掛金月額は次の16種類の金額があります。
| 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
|---|---|---|---|
| 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
| 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
短時間勤務の従業員(パートやアルバイト)は、上記の掛金月額のほかに特例掛金月額として次の3種類を選択できます。
| 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
掛金は、「月額変更申込書」を提出することでいつでも増額することができます。ただし、減額が可能なのは、減額に従業員が同意した場合、または、掛金月額を払うことが難しいと厚生労働大臣が認めた場合に限られているため、注意が必要です。
掛金月額の助成
初めて中退共制度に加入する事業主の場合、加入後4か月目から1年間、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を国が助成します。例えば従業員10名、1人当たり10,000円を掛金として払っている場合には、次のように60万円が助成されることになります。
10,000円×1/2=5,000円
5,000円×10人=50,000円
50,000円×12ヶ月=600,000円
親族のみを雇用する企業については助成の対象にならないため、注意しましょう。また、短時間従業員については次の金額が助成されます。
| 掛金金額 | 助成金額 |
|---|---|
| 2,000円 | 300円 |
| 3,000円 | 400円 |
| 4,000円 | 500円 |
月額変更助成
金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額した月から1年間、増額分の3分の1を国が助成します。例えば、従業員10名の掛金10,000円を、6,000円増額して16,000円にする場合、次のように1年で24万円が助成されることになります。
16,000円-10,000円=6,000円
6,000円×1/3=2,000円
2,000円×10名=20,000円
20,000円×12ヶ月=240,000円
ただし、月額掛金が20,000円以上からの増額は助成の対象になりません。また、親族のみを雇用する企業については助成の対象にならないため注意しましょう。
掛金月額の決め方
掛金月額は賃金や役職を基準にして決める方法や、定年や勤続年数等を基準にして退職金額を決め、掛金月額を逆算する方法があります。
| 賃金 | 掛金金額 |
|---|---|
| 16万円未満 | 8,000円 |
| 16~12万円未満 | 10,000円 |
| 20~24万円未満 | 12,000円 |
| 24~28万円未満 | 14,000円 |
| 28~32万円未満 | 16,000円 |
| 32~36万円未満 | 18,000円 |
| 36~40万円未満 | 20,000円 |
| 40万円以上 | 22,000円 |
| 役 職 | 掛金月額 |
|---|---|
| 一般社員 | 5,000円 |
| 主 任 | 8,000円 |
| 係 長 | 12,000円 |
| 課長補佐 | 18,000円 |
| 課 長 | 24,000円 |
| 部 長 | 30,000円 |
| 勤続年数 | 掛金月額 |
|---|---|
| 2年未満 | 5,000円 |
| 2~5年未満 | 8,000円 |
| 5~10年未満 | 12,000円 |
| 10~15年未満 | 18,000円 |
| 15~20年未満 | 24,000円 |
| 20年以上 | 30,000円 |
例:定額方法
勤続35年で退職金1,000万円とした場合、掛金月額は20,000円となります。
まとめ
中退共制度に加入して掛金月額を支払うと、従業員に対する退職金が支払うことができます。多額の退職金をまとめて用意することが難しい中小企業にとっては、非常にメリットがある制度です。
初めて中退共制度に加入した経営者の場合、加入して4ヶ月から1年間だけ掛金月額の1/2を国が助成してくれます。事業を起こしたばかりでまだ資金が溜まっていない中で退職金制度を導入したいと考えている中小企業にとっては、ありがたい制度だと言えるでしょう。
-
01
中退共は非課税
さらに、中退共制度を利用すると、税金対策につながります。現金・預金で退職金を積み立てようとした場合、税金を支払った後の税引後利益から積み立てないといけません。しかし、中退共制度の掛金金額は損金として扱われ、会社の資産として残らないので、税金がかからないのです。
また、中退共制度への掛金金額は従業員の給与ではないので、所得税として課税されることがありません。
-
02
中小規模には、柔軟な補償のある保険が重要
会社経営で多額の費用が必要となるシーンはいくつもあります。事業によって事故が発生した際、損害賠償責任を負うことになり、請求額を支払わないといけないことも。数千万円以上の支払いを裁判所から命じられることがあり、経営が圧迫されます。中小企業ならばすぐに会社自体が存続の危機に陥ってしまうことも考えられるでしょう。そのため、どんなトラブルに対しても柔軟に対応・補償してもらえる包括的な法人向けの保険に加入する必要があるのです。
-
03
保険は、補償範囲と、限度額や補償額が大事
条件に合う賠償責任保険がそろっている会社を選ぶ際には、会社が抱えるリスクに対して補償額で不足なくカバーできているのかをチェックしましょう。限度額も確認して高く設定できる保険商品かを確かめると良いですよ。限度額が高く設定できれば、万が一に備えておけるので支払金額が不足することがなく安心して会社を経営していけるでしょう。